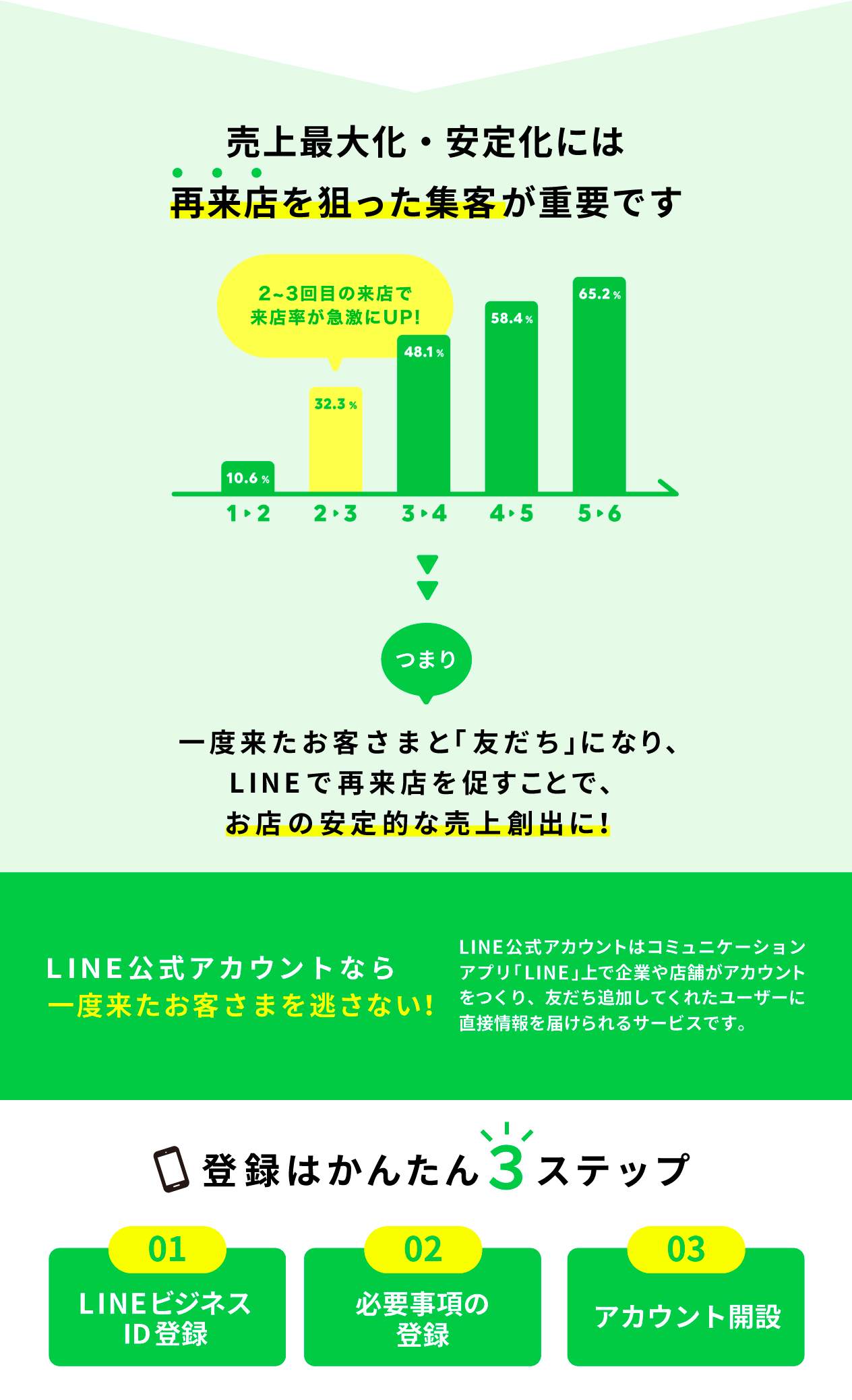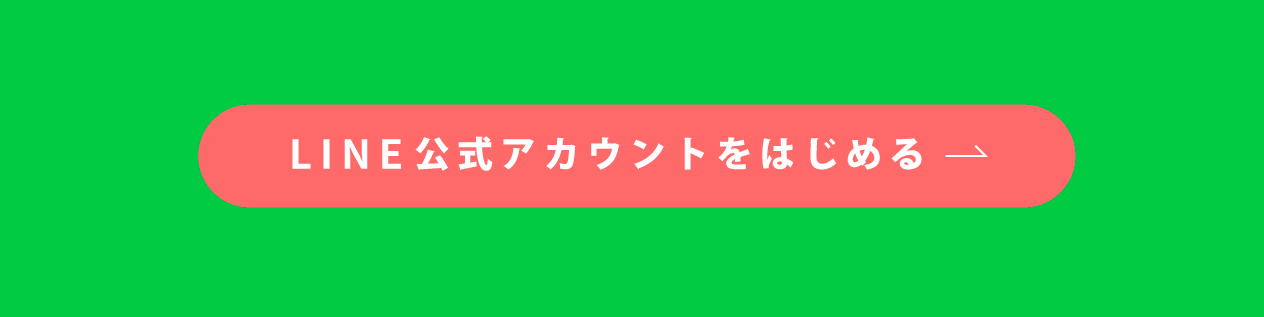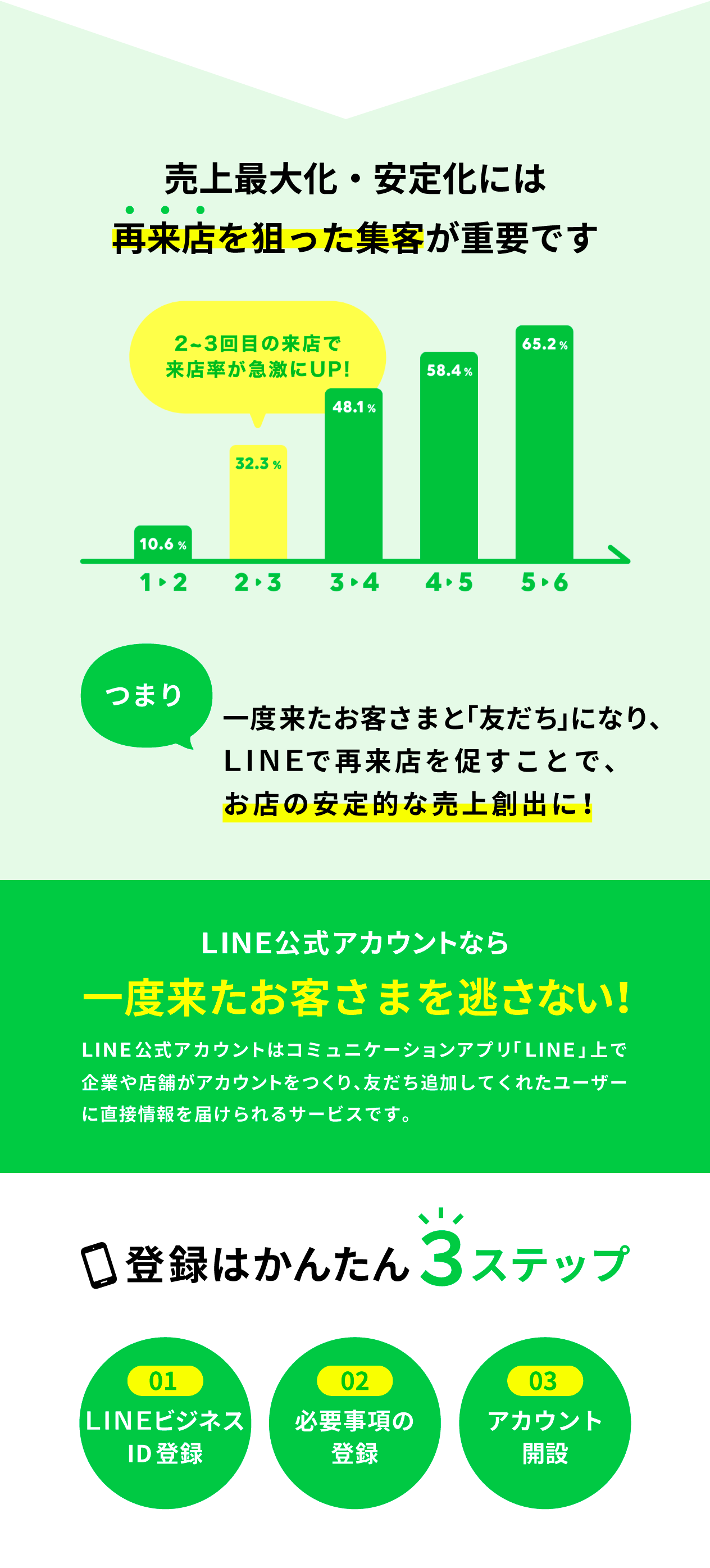酒場めぐりが好きで、お酒に関するコラム等を数多く手掛けるフリーライターのスズキナオさん。大阪在住のため、関西エリアにある酒場にフォーカスし、ご自身が通いたくなるお店について語っていただきました。
- サラリーマン時代、「大衆酒場」の魅力にハマる
- 古い酒場を探し歩く楽しみを知る
- 東京とは少し異なる大阪の酒場
- 気に入ってよく通っている関西のお店3軒
- 通ってしまうのは、その店の空気をつくり出す“人たち”に会いたいから
サラリーマン時代、「大衆酒場」の魅力にハマる
2023年現在、私は大阪に住み、フリーライターとして仕事をしている。大阪に引っ越してきたのは10年ほど前で、それまでは東京で暮らしながらIT系の企業に勤めていた。
勤務先は渋谷だった。仕事が終わるとよく同僚と渋谷の街で酒を飲み、一日の憂さを晴らすのだった。私が仕事帰りによく酒を飲むようになった15年ほど前は、吉田類氏の飲み歩き番組『吉田類の酒場放浪記』がスタートしたり、倉嶋紀和子氏が編集長を務める雑誌『古典酒場』が創刊されたりと、今思えば“大衆酒場ブーム”のようなものが生まれつつあった頃だと思う。
ずっとそういった店に通い続けてきた方にとっては「何を今さら」という話だと思うが、そのブームの大きな影響を受けた私にとって、大衆酒場はまったく新しい世界を垣間見せてくれるものだった。
それまでの私は、食べるものに対してほとんど執着がなく、「安くてお腹がいっぱいになればそれでいい」と、極端に言えばそんなふうに考えていた。お酒はよく飲んでいたが、同じような理由で、いつも決まった格安チェーン居酒屋に行ってばかりだった。
大衆酒場の多くは、チェーン店とは違って、その店ごとの個性がある。焼鳥の煙がもうもうと立ち込める賑やかなお店もあれば、寡黙な店主が腕をふるった料理を、静かに味わう客ばかりの店もある。少し緊張しながらのれんをくぐり、その店の空気に徐々に身を浸していく行為は、一回一回が貴重な体験として心に残るのだった。
古い酒場を探し歩く楽しみを知る
大衆酒場めぐりにすっかりハマった私は、酒好きの同僚と東京のあちこちに酒場を訪ね歩くようになった。しっかり数えたわけではないが、短い期間に100軒ほどはめぐっていたのではないか。
勤め先のある渋谷エリアにも、探せば古い酒場が残っているもので、そういう場所を探し歩くのが特に好きだった。経験を重ねるうち、歩き慣れていたはずの街の中に、今まで見落としていた酒場を発見したりして、「自分のレベルが上がったからこそ見つけられたのだ」と悦に入るのだった。
初めて入る店の椅子に座り、メニューを見ながらその店の雰囲気を探る。「他のメニューは安いのに、このメニューだけちょっと高いぞ。よっぽど手間をかけて作った名物なのかも」とか、そんなことを頭の中で考えながら注文してみたり、たまに隣の席の常連さんがお店のことを教えてくれたり、そういう時間がたまらなく好きだ。
東京とは少し異なる大阪の酒場
大衆酒場をめぐることで、住み慣れていた東京の別の魅力が見えてきた頃、先述の通り、大阪へ生活の拠点を移すことになった。大阪に来てみると、東京とはまた違った酒場の熱気に圧倒された。
現在、私は大阪市内に住んでいるのだが、大阪市内にもまだまだ昔ながらの商店街が残っており、その多くが行き交う人で賑わっている。そして、そんな商店街の近くにはたいてい素晴らしい酒場が見つかるものだ。
そういう店にお邪魔させてもらうと、周囲から大阪弁の軽快な会話が聞こえてきて、「ああ、自分は大阪で暮らしているんだな」と強く実感するのだった。「大きな駅や商店街の近くには必ずいい大衆酒場がある」というのと、「酒場のつまみとお酒がだいたい安い」、「午前中から営業している酒場がすごく多い」といったあたりが、個人的に大阪の酒場に感じる特殊性だろうか。
もちろん、東京にも好きな酒場はたくさんあるが、都市としての規模が違うこともあってか、いい酒場はポツンポツンと遠く離れて点在している印象がある。あるいは、立石や赤羽といった、名酒場が集中するような地域にまとまっている場合が多く、大阪のように、あちこちの街の生活と多くの酒場とが地続きに存在するようなケースにはなかなか出会えなかった記憶がある。
気に入ってよく通っている関西のお店3軒
今回は私が暮らす大阪を含め、特に気に入って通っている関西のお店を3つ紹介したいと思う。
多くの酔客に愛された「立ち飲み処 こばやし」店主の姿勢
歩けば歩くほど際限なくいい店が見つかって困ってしまう大阪の街。あちこち散策しては酒場をめぐってきたが、特に心に残っているのが、大阪市此花区・西九条にあった「立ち飲み処 こばやし」という店である。厨房を囲むコの字カウンターにいつも多くの酔客が立ち並び、活気のある店だった。

おつまみのメニューは煮込み、おでん、その時々の惣菜類と、いわゆる大衆酒場的なオーソドックスな品揃えだったが、どれも心が落ち着くような優しい味わいだった。しかし、常連さんたちはよく「この店にはな、何が美味しいだとか、そんなのはないねん。ただこの場所がええねん」と言っていた。
そんな「立ち飲み処 こばやし」は阪神電車の西九条駅の高架下の店で、改修工事に伴って、2020年10月末に約40年という長い歴史を終えた。
私は何度かその店に行き、いつもいい時間を過ごさせてもらった。閉店が近いある日、店主の小林静江さんにインタビューをさせていただいたことがあった。さまざまなお話の中で印象的だったのが、静江さんの常連客に対する考え方だった。

静江さんは「うちは一見さんを一番大事にするの。常連さんは放っておいても勝手にやってくれるから」と言うのだ。
確かに私も初めて「立ち飲み処 こばやし」に行った時から、静江さんに優しくしていただいた記憶がある。周りの常連さんもみんな気さくで、静江さんに「こらっ!」と時に叱られながらも楽しく飲み、初心者の私にいろいろと教えてくださった。
勝手がわからず困っている一見客こそ手厚くサポートし、店の雰囲気やおおよそのルールを知っている常連さんにはそれぞれの自治に任せるという、その姿勢。その考え方があってこそ、店の風通しのよさ、あたたかさが生まれていたのだと思う。
そして、お客さんはみんな、そのような場があることの貴重さを感じていたはずだ。実際、「立ち飲み処 こばやし」は最後の最後まで数多くの酔客に愛され、大団円の中で営業を終了したのだった。

ちなみに閉店後は、娘の典子さんが中心となり、大阪市東住吉区で「フライ屋こばやし」という惣菜店を営業している。静江さんもたまにお店に立ち、忙しく働く典子さんをサポートしていて、静江さん仕込みの、つまり「立ち飲み処 こばやし」の味そのままの惣菜がメニューに並ぶこともある。かつての常連もよく静江さんの顔を見にやってくるんだとか。
「立ち飲み処 こばやし」に出会い、静江さんのお話を聞いて、自分が好きだと感じる店の共通点が徐々にわかってきた気がした。常連さんと一見さんの垣根を感じさせない雰囲気、誰であってもその人なりの楽しみ方ができるような店を、私は探し歩いているのだ。
そんな店を求めるなら、チェーン店が一番なのかもしれない。チェーン店には常連も一見もない。だが、チェーン店のようにシステムが行き渡った店ではなく、あくまで個人個人の集まりとして居心地のいい場が生まれるからこそ、それが奇跡のようにありがたく感じられるのである。
長年通ってきたかのように温かく迎えてくれる「皆様食堂」
大阪に来て10年ほどがたち、少しずつではあるが、お気に入りの店が増えてきた。例えば、神戸・三ノ宮の高架下にある「皆様食堂」は、たまに無性にお店の空気を感じに足を運びたくなるような酒場だ。
白いのれんには「家庭の延長 皆様食堂」とある。1960年代からこの場所で営業を続けているそうで、Uの字型のカウンターに10人ほどが座れる小さな店内は、いつも活気にあふれている。

壁には短冊メニューが所狭しと貼られていて壮観だ。この店の特徴の一つが、厨房が2階部分にあること。客席のある1階から2階の厨房へと、潜水艦の“伝声管“のようなパイプでオーダーを通す場面は、いつ見ても胸が高鳴る。このパイプがあるおかげで、お客さんがみな一つの船に乗っているような一体感が生まれるのかもしれない。

ここもまた店主の客あしらいが素晴らしく、私のようにたまにしか現れない客も気さくに受け入れてくれる店である。そして、席に座ってしまえば、まるで長年そこに通ってきたかのような居心地のよさを感じさせてくれるのだ。
常連さんらしき方もいるし、かと思えば若い女性が二人組で飲んだりもしているし、海外から来て日本で仕事をしているという方がふらっとやって来て「おお!よう来たな」と常連さんにあたたかく迎えられたりもしている。
雰囲気も素晴らしいが、とにかく、料理がどれも美味しい。特に好きなのが名物のおでん。長年にわたって継ぎ足しているというだしは濃く、そこで煮込まれた大根は飴色である。注文するといつも人数分に切り分けて出してくれて、その気遣いがうれしい。だしの旨味は具材一つ一つの中までしっかりとしみ込んでいるが、意外にも後味はあっさりしている。

また、「豚汁」「野菜汁」「豚もやし汁」など、バリエーションが多彩な汁物メニューが用意されているのもうれしい。「いつかこの店の汁物をコンプリートしよう」と目標を掲げてはいるが、気になるおつまみをいろいろ食べているうちに満腹になってしまう。そもそも締めの汁物にたどり着けない時がほとんどなので、一体いつになればこの店のメニューの全容を知ることができるのか、途方に暮れるような気分である。
常連と一見客の境を感じさせない「高木与三右衛門商店」
もう一軒、割と最近知ってすごく好きになったのが京都・西大路御池にある「高木与三右衛門商店」である。多くの人に「高木商店」と呼ばれ、親しまれている。

1939年創業の酒屋の一角で飲食ができる、いわゆる角打ちスタイルの店なのだが、店内は常に綺麗に磨かれ、手のかかっていそうなおつまみが、安価に提供されている。冷蔵ケースから好きな小鉢を取ってもいいし、黒板メニューから選んでオーダーしてもいい。スナック菓子などの乾きものや、カップラーメンまであって、どんな気分にも対応してくれる。

二度目にお店に入った時、常連さんに「ここが特等席やで!」と店の奥に導いていただいた。そこは店主のお母様が立っている場所で、お酒を作る姿、会計時にそろばんをはじく姿を間近に見ることができた。こんないい場所をほぼ一見客の私に教えてくれる常連さん、なんとあたたかいことか。
その常連さんが飲んでいた「ミドリ」という飲み物を真似して注文させてもらうと、甲類焼酎をお店特製の濃い抹茶で割ったもので、これがとても美味しくてすっかり気に入ってしまった。

「高木与三右衛門商店」もやはり、常連と一見客の境を感じさせない店である。適度に放っておいてくれる感じがありつつ、その裏に頭が下がるほど細やかな配慮があるように思える。
いつまででも長居してしまいたくなるが、「高木与三右衛門商店」は人気店だ。自分が気さくに受け入れてもらったように、次に来る人のためにも適度なところで切り上げる。そして、また次にこの店に来て飲めるのを楽しみにしながら帰路につく。
通ってしまうのは、その店の空気をつくり出す“人たち”に会いたいから
一見客に対して気さくである点ばかりを強調してしまったが、どこの店ももちろん、常連さんを大事にしていることは間違いない。それが前提としてあった上で、新しく来る客にも開かれている。そういう店が私は好きなのだ。
先日、知人とこんな話をした。例えば、ある飲食店に対して「あそこの名物料理は絶品で、接客も素晴らしい」と、私たちはその店の特徴を簡単に言葉で捉えた気になってしまうけど、実際にその店に行ったからといって、全員が同じ体験をするわけではない。
お店の方と話がはずんで、何か一品サービスしてもらえることもあるかもしれないし、逆に、場の雰囲気を壊してしまって素っ気ない対応をされることだってあるだろう。友人が勧めてくれた店と私との相性が必ずしも一致するとは限らない。お店の方も客もそれぞれの内面を持った人間だから、いつも同じなわけがない。ある人にとって苦手な味が、ある人にとっては大好物だということが当たり前にあるように、感じ方もそれぞれだ。
それなのに私たちはいつの間にか、店に対して「お金を払えば一定の見返りがあって当然だ」と考え過ぎてはいないだろうか。チェーン店ならまだしも、個人規模の店にそれを求めるのは、そもそもおかしなことなのではないか。その店にいる全員が優劣なく、力を合わせていい時間を作ろうと少しずつ歩み寄るような、そんな態度が必要なのだと思う。
店に飲みに行く時、結局のところ、私は人に会いに行っているのだと思う。お店の方や、その店を愛する常連さんや、私のような一見客も含めた、その空間にいる全ての人々によって作られている居心地のいい場を体験したくて、また飲みに行くのだと思う。
あの人の通いたくなるお店は?
【著者】

スズキナオさん
東京生まれ・大阪在住のフリーライター。散歩と酒場めぐりを趣味とし、同じライターのパリッコさんと酒場や酒の文化を追求するユニット「酒の穴」を結成。日常を切り取るエピソードやお酒関連のエッセイなど多数執筆している。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと(スタンド・ブックス)』、パリッコさんとの共著に『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門(エレキングブックス)』など。
Twitter:@chimidoro
ブログ:スズキナオ
編集:はてな編集部